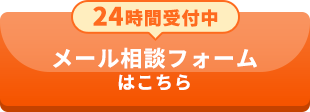特別受益の持ち戻しと計算方法について
相続において、特別受益の持ち戻しが問題になるケースは多々あります。
しかし、特別受益という言葉自体、聞き慣れないという方がほとんどなのではないでしょうか?
相続という制度は、原則的には不公平にならないように法定相続分といって、相続人それぞれがこのように相続すべきという持ち分が民法にて定められています。
しかし、実際には一部の相続人が、被相続人から生前に生前贈与を受けていたなどの理由で、法定相続分による分配自体が公平にならないケースも存在するのです。
そこで、相続では生前贈与などによって相続財産から前渡しを受けていた方に対して、その受け渡し分をいったん相続財産に戻した上で、相続分を計算しなおすことで公平を図っていて、これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
特別受益に該当するのはどんなときか
最初に、どういった場合に特別受益に該当するのかについて知っておきましょう。
特別受益は、遺言書による贈与、婚姻、または養子縁組の際の贈与、生活を営む上での援助としての贈与、などが該当します。
その中でも、他の相続人がもらっておらず、特定の相続人だけが上記したような贈与を受けていた場合、特別受益の持ち戻しによる公平化を図ります。
ただし、近年の法改正により、生前贈与についての持ち戻しは、相続開始前の10年間に限定することになりました。
以前まで、何年前にあった生前贈与でも、特定の相続人だけが特別受益を受けていると判断できた場合には、持ち戻しの対象となっていたのですが、2019年7月1日以降の相続については、相続開始前の10年間と期間が限定されることになったので注意が必要です。
持ち戻しの計算方法について
では次に、具体例を使って特別受益の持ち戻しの計算方法についても見ていきましょう。
特定の相続人が得た特別受益の金額について、特に争いがなければ計算はそれほど難しくはありません。
方法としては、特別受益分をいったん相続財産に戻し、その上で法定相続分による分配するというもの。
たとえば、相続人が被相続人の長男A次男Bだったとして、相続財産が700万円あったとします。
このまま法定相続分で分配すれば、それぞれ2分の1ずつ得ることになり、長男Aが350万円、次男Bが350万円となります。
しかし、長男Aは被相続人である父から、生計を営むための援助として過去に100万円の支援を受けていました。
よって、この100万円は特別受益の持ち戻しの対象となり、相続財産は800万円、そこから2分の1ずつを分配することになるため、それぞれが400万円ずつを得ることになりますが、長男Aはすでに100万円を得ているため、700万円の最終的な分配は、長男Aが300万円、次男Bが400万円となります。
特別受益は揉めやすい要因の1つ
上記からもわかるように、特別受益の持ち戻しの計算はそれほど難しいものではありません。
しかし、特別受益自体に争いがある場合や、金額が確定できていない場合、非常に揉めやすい要因の1つとなります。
法改正によって、10年という期間の限定ができたものの、その当時の領収書や合意書、そういった類の金額がわかる証明を手元に残している可能性は低く、いったいどの程度の特別受益があったのかについて、揉めてしまうケースが多々あります。
よって、預金通帳の履歴や、手紙、メモ、日記など、贈与の金額を証明できる資料の有無が重要となります。
被相続人が生前であれば、どの程度の贈与があったのか確認することも可能ですが、すでに亡くなっているとなれば、確認するのは簡単ではありません。
特別受益を受けた者としても、金額を裏付ける資料がなければ、低い金額を申告しても確認のしようがないと考えることもあります。
また、自身の取り分に何百万と金額の差異が出てくるとなれば、申告だけでは信用できないといったように、相続人全員が疑心暗鬼になる可能性も十分にあります。
となれば、遺産分割協議は停滞し、最終的には調停や審判といった手続きによらなければ解決を見込めない事態にまで発展する恐れもあるのです。
調停や審判は数日程度で終わる手続きではなく、話し合いの行われる期日は月に1回程度、長いと1年以上かかることもあります。
こうした泥沼状態に陥らないためにも、話し合いの進展が難しいと感じた時点で、弁護士といった専門家に相談されることをおすすめします。
被相続人の意志で持ち戻しの免除は可
上記をご覧になった方で、「じゃあ贈与ってなんの意味があるの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
結局、相続財産の中に持ち戻されてしまうのであれば、まったく意味がありません。
そこで、持ち戻しは被相続人の意志によって免除することが可能となっています。
たとえば、遺言書による贈与の場合、「この贈与については特別受益の持ち戻しは免除する」といった記載があれば、その贈与に該当する財産が持ち戻されることはありません。
そして、生前贈与の場合は、黙示の意思表示でも構わないとされています、。
たとえば、自宅である不動産を生前贈与する代わりに、その相続人には一緒に家に住んでもらい、介護してもらっていたといった場合、持ち戻しの免除の意思表示として認められたことが過去にありました。
とはいえ、持ち戻しの免除があったとしても、遺留分の侵害だけはできないため、遺留分を侵害するほどの不公平すぎる遺言書や生前贈与に対しては、遺留分侵害額請求によって対処しましょう。