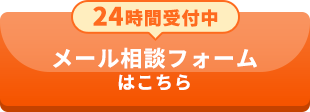遺言書はどういった場合に無効になるのか?
遺言書を作成することで、将来の相続についての心配が減るのは言うまでもありません。
相続人同士、揉めることなく遺産分割を終えられれば何よりです。
しかし、遺言書というのはちょっとしたことで無効になってしまうデリケートな書面。
これは自筆証書遺言に限らず、秘密証書遺言はもちろん、公正証書遺言であったとしても無効になるケースがあります。
そこで今回は、自身が遺言書で失敗しないためにも、遺言書はどういった場合に無効になるのかについて見ていきましょう。
遺言書に日付の記載がない
遺言書に自身の署名捺印をするのは多くの方が注意しているのですが、日付の記載を忘れる方が非常に多いのです。
日付の記載がない遺言書はすべて無効となるので注意しましょう。
その他にも、「〇年〇月吉日」といったように作成の日付が確定できないような記載もアウトです。
一方で、「〇歳の誕生日」といったように、日付の確定ができる場合は無効にはなりません。
しかし、いらぬ誤解を招かないように、しっかりと作成の日付を記載しておくようにしましょう。
なお、遺言書の日付についてのちょっとした豆知識ですが、遺言書が複数存在する場合、どの遺言書を優先するかについては日付で決められます。
なぜなら一番新しい日付で作成された遺言書が、被相続人の最後の意志になるためです。
遺言書にとって日付は非常に重要になってくるため、必ず書き忘れないように注意しましょう。
ちなみに、私の経験で、実際の作成時とは異なる日付を年単位で誤って記載してしまった遺言書について、裁判官によって無効ではないかという見解が示された案件があります(但し判決ではなく和解によって解決)。
当然ながら、記載忘れのみならず記載間違いも念のため注意する必要がありますね。
パソコンで作成した遺言書
近年ではパソコンを使っている方も本当に増えてきました。
中には遺言書をパソコンで打ち込んで作成したいと考える方も多いのではないでしょうか?
しかし、パソコンで作成された遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は全文を自筆で書かなければならないと規定されています。
ただ、近年の法改正により若干変更があり、遺産目録についてはパソコンで作成しても問題がないとされています。
自筆証書遺言であっても、全文自筆で作成する必要はなくなり、僅かながらの負担軽減となりました。
なお、上記は自筆証書遺言の作成時に限り、秘密証書遺言についてはパソコンで作成しても問題はありません。
ただし、秘密証書遺言は公証役場に持ち込む必要があるため、この2つの作成方式の違いについては間違いがないように注意してください。
加筆や修正手順を間違えている遺言書
遺言書を自身で作成する場合、遺産目録をパソコンで作成できるようになったとはいえ、自筆すべき箇所が多いことに違いはありません。
そして、書き間違えがあった場合、みなさまだったらどのように対処するでしょうか?
その多くは、二重線を引いたり、修正ペンで消したりし、その上に訂正するという方が多いはずです。
しかし、遺言書には加筆修正の手順が定められていて、上記のような方法で加筆修正がなされていた場合、その遺言書は無効になってしまいます。
そして、その手順は非常に面倒なものとなっていますので、もし、作成中に書き間違えがあった場合は、横着して無理に加筆修正するのではなく、潔く新しく作成しなおすことを強くおすすめします。
遺言の内容を第三者が特定できない場合
遺言書というのは、相続人に向けて作成されるものですが、その内容は第三者であってもしっかり特定できる内容でなければなりません。
特に不動産や預貯金については、明瞭に書かねばならない点には注意が必要です。
たとえば、不動産であれば、単に「自宅」や、「〇県の土地」といった書き方ではなく、不動産の登記簿謄本に記載されている内容(所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積など)についてきっちりと記載しなければなりません。
同様に預貯金であれば、銀行名、支店名、口座名義、預金の種類に番号まで記載が必要です。
身内だけ、相続人だけが理解できる書き方をすると、その遺言書は無効になってしまうので注意しましょう。
なぜなら、相続手続きの際、各機関が遺産の特定をできなくなってしまうためです。
不明瞭な遺言書では、相続登記や預貯金の名義変更といった手続きはできなくなってしまうと覚えておきましょう。
被相続人の意志ではない遺言書
これから自らの意思で遺言書を作成しようと検討されている方にとってはあまり関係ないかもしれませんが、遺言書が無効となる例外パターンとしてご紹介います。
それは、被相続人の意志で作成されていない遺言書です。
どういった場合に該当するかというと、遺言能力がない状態(認知症など)で作成された遺言書である場合や、他者からの脅迫といった強硬手段を背景に無理やり作成された遺言書である場合などです。
特に前者の場合、遺言作成時に認知症であったかどうかの判断は難しく、これを証明するのは簡単ではありません。
ゆえに当時の被相続人の遺言能力をめぐって争いへと発展するケースは本当によく見られます。
たとえ公正証書遺言であっても、作成時に遺言能力がなかったとして、後から無効になったケースも現実にはあります。
近年では、こうしたトラブルを防止するため、公証役場でも慎重に遺言書の作成がなされるようになりました。
また、自筆証書遺言の場合、遺言作成の様子を撮影しておくといった方法を取られる方もいます。
このように遺言書は、作成の段階から有効無効が問われる、非常に繊細な書面なのだと覚えておきましょう。
これから作成を検討されている方は、ぜひ肝に銘じて作成へと臨んでください。